成年後見制度とは|後見人になれる人や費用など成年後見人を分かりやすく解説
- 橙縁社公式

- 2025年9月4日
- 読了時間: 8分
『成年後見人』という言葉を聞いた事がある方は、多いのではないでしょうか。
では、実際の内容や費用、誰が『成年後見人』になれるか等、具体的には分からない人が多いのも現状です。
まず、『成年後見制度』は、
認知症
知的障害
精神障害
などにより、判断能力が不十分な方を、財産管理や身上保護の面で支援する制度です。
そして、『成年後見制度』は、
法定後見制度
任意後見制度
の2種類に分かれ、それぞれ利用の仕方や後見人の選任方法が異なります。
そこでこの記事では、『成年後見制度』の内容や選任方法、費用や誰がなれるのか等について紹介していきます。
『葬儀費用が高過ぎた。。。』
『葬儀内容がイメージと違った。。。』
葬儀トラブルを回避するためには、葬儀の事前相談が最も有効!!
葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
成年後見制度とは|後見人になれる人や費用など成年後見人を分かりやすく解説
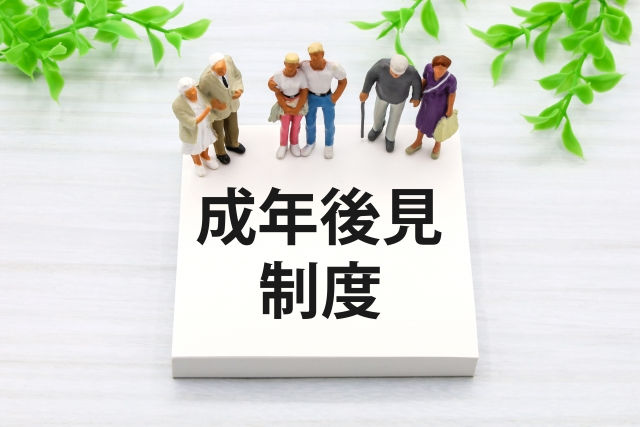
『成年後見制度』の目的は、
財産管理
身上保護
悪徳商法からの保護
となっており、制度を利用する場合、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで相談することができます。
そして、家庭裁判所への申し立てが必要なケースもあります。
成年後見制度の目的【1】財産管理
預貯金や不動産などの財産を管理し、無駄遣いや不当な請求から守ります。
成年後見制度の目的【2】身上保護
介護サービスや施設入所などの契約手続きを行い、本人の生活や医療・福祉サービスが円滑に受けられるように支援します。
成年後見制度の目的【3】悪徳商法からの保護
判断能力が低下している間に、不利益な契約を結んでしまうことを防ぎ、悪徳商法の被害から本人を守ります。
法定後見制度と任意後見制度の違いとは?

冒頭で触れたように、『成年後見制度』には、
法定後見制度
任意後見制度
の2種類に分かれます。
では、この2種類にはどのような違いがあるのでしょうか?
法定後見制度とは
『法定後見制度』では、
認知症
知的障害
精神障害
などによって、判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
選任方法は、家庭裁判所が本人の状況に合わせ、適切な後見人を選びます。
任意後見制度とは
『任意後見制度』では、
本人の判断能力が十分なうち
に、将来判断能力が低下した際、あらかじめ信頼できる任意後見人と、任意後見契約を結んでおく制度です。
契約は公正証書で締結する必要があり、本人自身が後見人や委任する内容を決められます。
全く同じ内容の『お葬式』なのに、
A社 ⇨ 80万円
B社 ⇨ 120万円
C社 ⇨ 200万円
と、葬儀社によって非常に大きな葬儀費用の金額差があります。
葬儀費用に不安・疑問がある方は、下記をクリック!!
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
どんな人が成年後見人になれるのか?

実は、『成年後見人』になるために、特別な資格は必要ありません。
そのため、信頼して財産管理などを頼める人となる訳ですが、
本人の家族、親族
弁護士、司法書士など専門家
研修を受けた市民後見人
社会福祉法人などの法人後見
が一般的な候補者ですが、家庭裁判所が適性を判断して選任すれば、誰でもなれる可能性はあります。
*原則として、以下の欠格事由に該当しない必要があります。
未成年者
破産者
本人との関係で不利益を及ぼす可能性がある
本人の訴訟代理人、代理人または補助者である者で、被後見人との間に不和(候補者が高齢、候補者を親族に含めないなど)がある場合
一般的な後見人の候補者【1】本人の家族、親族
被後見人の家族や親族が後見人に選ばれることもあります。
ですが、後見の業務負担や専門性から、専門家に選ばれるケースが増えています。
一般的な後見人の候補者【2】弁護士、司法書士など専門家
最も後見人に選ばれるのは、やはり専門家でしょう。
弁護士・司法書士・社会福祉士など、法律や福祉の専門知識を持つ専門家です。
一般的な後見人の候補者【3】研修を受けた市民後見人
後見制度に関する研修を受けた市民が、地域貢献の一環として後見人を務めることがあります。
一般的な後見人の候補者【4】社会福祉法人などの法人後見
社会福祉法人やNPO法人などの公益法人も成年後見人として選任されます。
成年後見人に依頼した際に掛かる費用は?

成年後見人の費用は、
制度利用時の申立て費用
後見開始後の月額費用
専門家への依頼費用
が掛かり、専門家に依頼する場合は、追加費用が発生します。
成年後見人の費用【1】制度利用時の申立て費用
申立て費用は、家庭裁判所に後見開始の申立てを行う際に掛かる費用です。
平均的には約15~50万円が目安となります。
収入印紙、郵便切手代
*官邸費用が必要な場合で10万円程度、そのほかに数千円が必要です。
専門家への報酬
*弁護士や司法書士に、申立て手続きを依頼する場合、10~30万円程度の報酬が掛かります。
成年後見人の費用【2】後見開始後の月額費用
後見人への月額報酬は、家庭裁判所が決定しますが、
月2~6万円
が目安と言えるでしょう。
基本報酬
管理する財産の額に応じて、月額2~6万円が目安。
なお、財産が多い程、また管理が複雑な程、金額が高くなる傾向です。
付加報酬
不動産売却や遺産分割協議など、特別に困難な業務を行った場合、基本報酬の50%を上限として加算。
後見監査人への報酬
後見監査人が選任された場合、月額1~3万円程度の報酬が必要。
成年後見人の費用|番外編
本人が元気な内に契約を結ぶ『任意後見制度』の場合、申立て費用や専門家への報酬(公正証書作成手数料など)が発生します。
また、家族が後見人になった場合、報酬が無料、もしくは低く設定されることがあります。
『葬儀費用が高過ぎた。。。』
『葬儀内容がイメージと違った。。。』
葬儀トラブルを回避するためには、葬儀の事前相談が最も有効!!
葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
成年後見人の依頼はどこに相談に行けばよいのか?

一般的に、成年後見人の依頼は、
家族や親族
弁護士、司法書士などの専門家
のどちらかで検討する方が多いかと思います。
しかし、本人自身の状況や費用など、別の相談窓口があれば、検討したいと考える方もいらっしゃいます。
そのような場合、どこに相談に行くのが良いのでしょうか?
市区町村の窓口
地域包括支援センター
社会福祉協議会
家庭裁判所
成年後見人の窓口【1】市区町村の窓口
全ての自治体ではありませんが、市区町村に設置されている窓口で相談できます。
成年後見人の窓口【2】地域包括支援センター
地域の福祉サービスを総合的に支援する、地域包括支援センターでも相談できます。
成年後見人の窓口【3】社会福祉協議会
地域の福祉活動を推進する、社会福祉協議会でも相談できます。
成年後見人の窓口【4】家庭裁判所
他の窓口と異なり全ての相談とはいきませんが、申立てが必要な場合、申立て手続きについて相談できます。
まとめ

今回は、『成年後見制度』の内容や選任方法、費用や誰がなれるのか等について紹介しました。
近年、おひとり様世帯が増えており、財産の管理や死後の手続きなどのため、
成年後見人
死後事務委任契約
を検討して、依頼する方が増えています。
昔は無料で家族が行っていた内容ですが、第三者に依頼するため当然費用は発生します。
ですが、現代社会を考えた時に、『任意後見制度』の活用は、新しい当たり前へとなっていくのでしょう。
葬儀に関するご相談は『橙縁社』へ

葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
葬儀費用が高かった
イメージと違った
これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
いざという時困らないように、葬儀全般の疑問は
橙縁社(とうえんしゃ)
にお問合せ下さい。
一級葬祭ディレクターの専門スタッフが、24時間365日対応させて頂きます。
葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
全く同じ内容の『お葬式』なのに、
A社 ⇨ 80万円
B社 ⇨ 120万円
C社 ⇨ 200万円
と、葬儀社によって非常に大きな葬儀費用の金額差があります。
葬儀費用に不安・疑問がある方は、下記をクリック!!









コメント